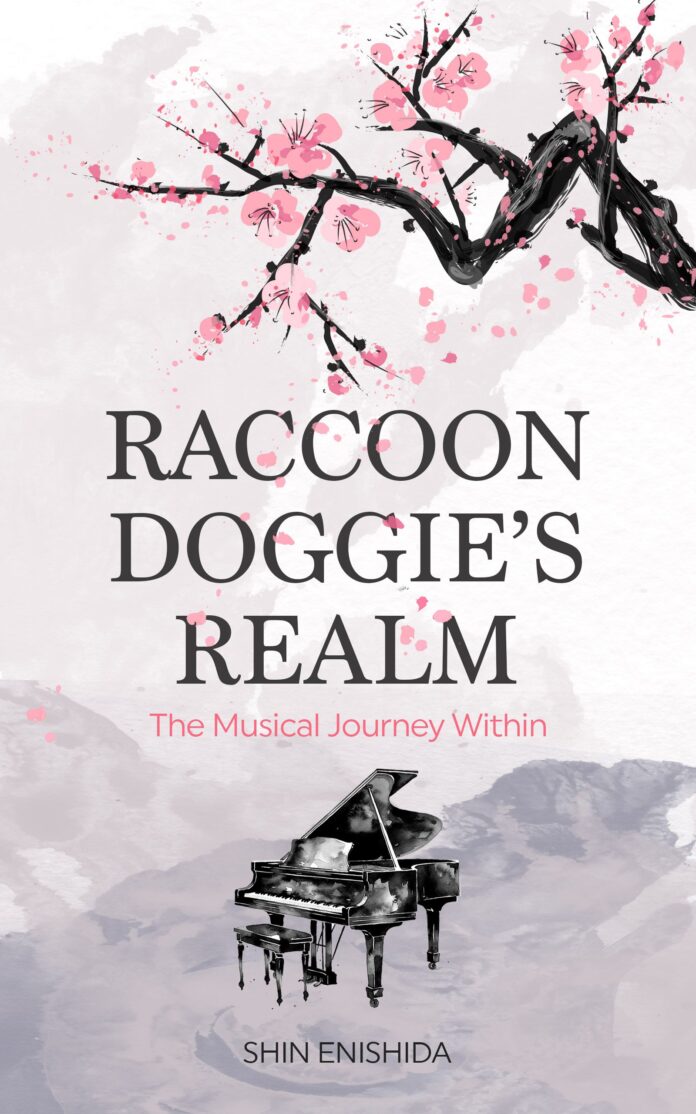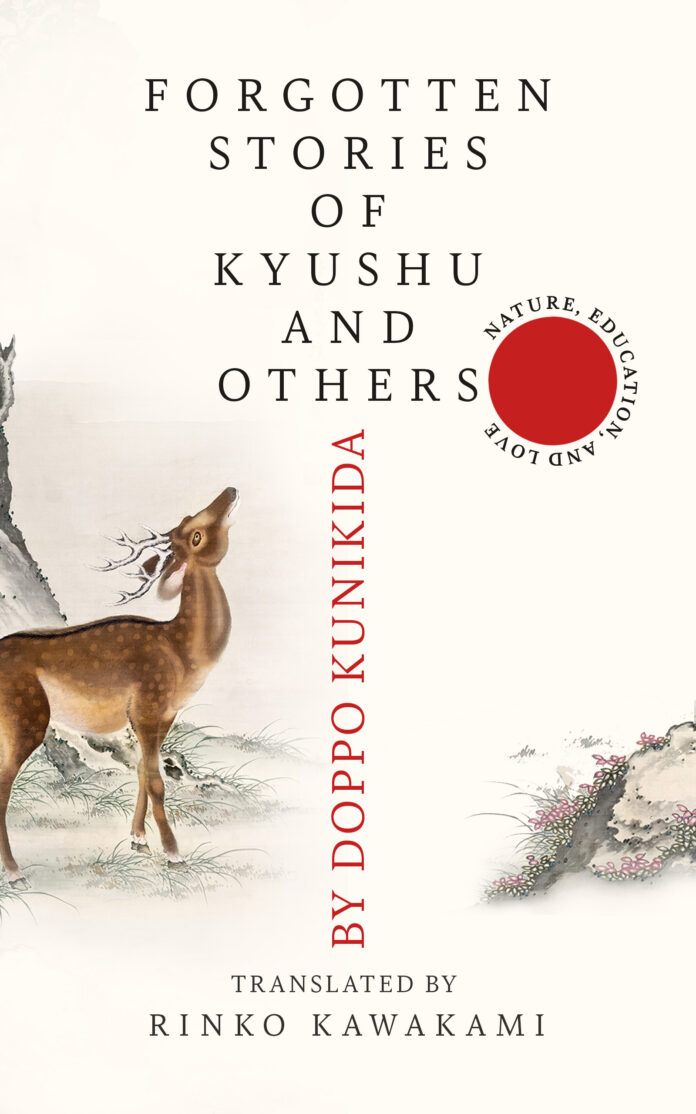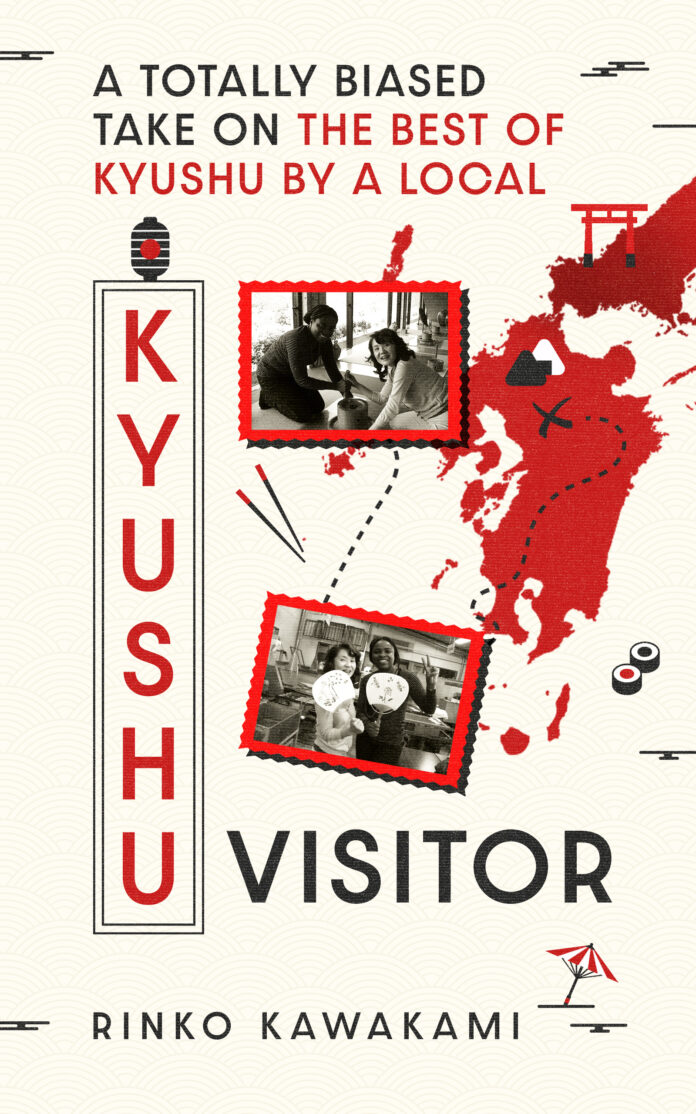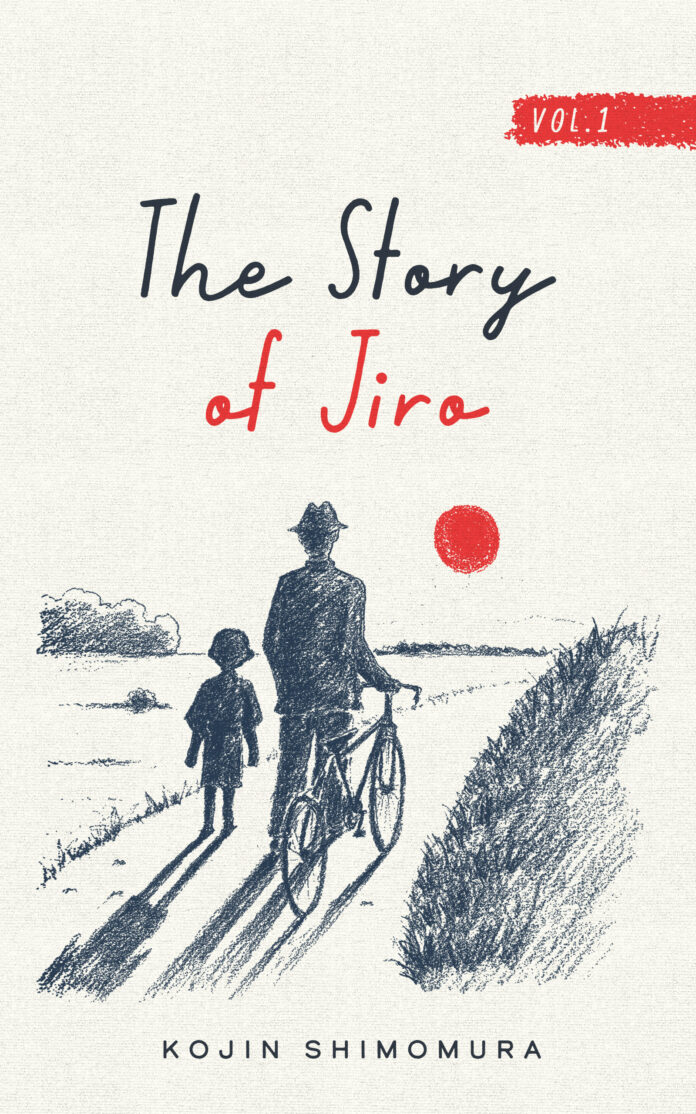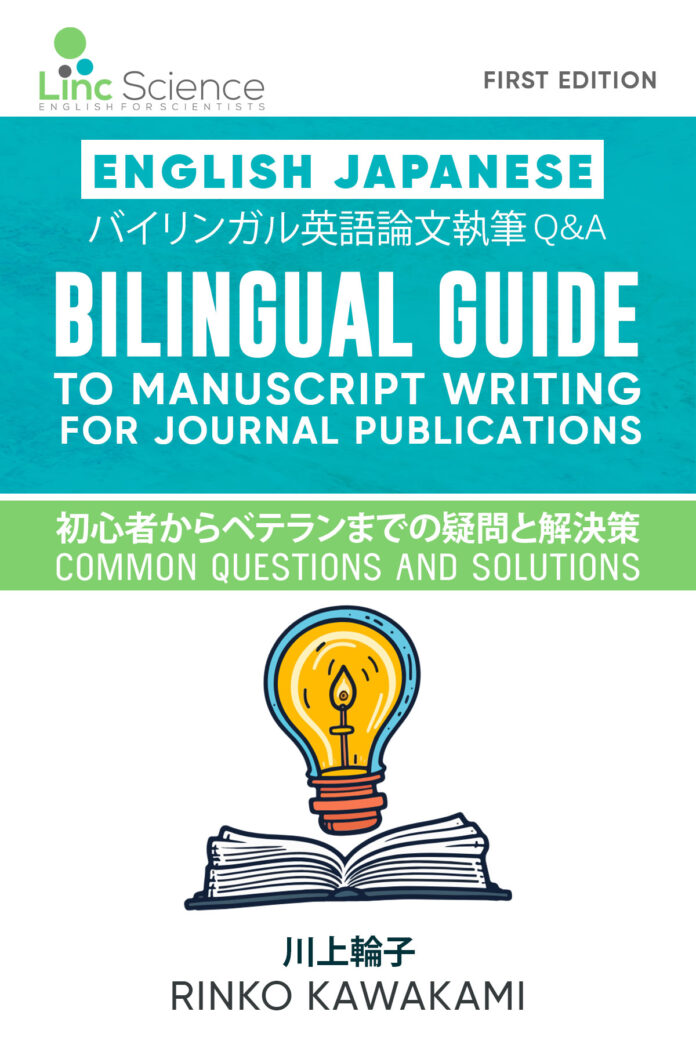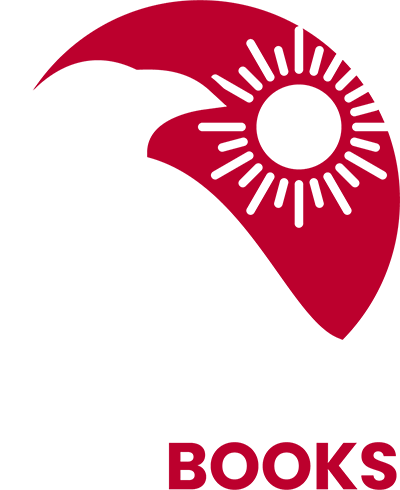和食を試してみたいけれど、どこから始めればいいかわからないなら…
ご存じの方も多いと思いますが、2013年に和食はユネスコの無形文化遺産に登録されました。これを受けて、「和食を試してみたいけれど、どこから始めればいいのだろう?」と悩んでいる方もいらっしゃるかも知れません。
そんな方には、まずとんかつ(豚肉の切り身に小麦粉、溶き卵、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理)を試してみることをお勧めします。とんかつは、和食初心者でも気軽に挑戦できる一品です。
とんかつは「洋食」から発展した和食だから初心者でも試しやすい
とんかつが初心者にも親しみやすい料理である理由は、日本においてとんかつはかつて洋食(西洋風の料理)とされており、そのルーツが1913年(大正時代初期)頃から広まったカツレツにあるからです。
この時代、日本の食文化は大きく変化し始め、肉を食べる習慣が広まり、洋食が人気を集めるようになりました。そして昭和初期には、それまで「カツレツ」と呼ばれていた料理が「とんかつ」という名前で知られるようになり、カレーやコロッケと並んで日本の「三大洋食」のひとつとして定着しました(阿古, 2021)。
とんかつが当時、洋食とみなされたのは、その調理法にあります。豚肉に衣をつけ、パン粉をまぶして揚げるという技法は、西洋料理から取り入れられたものでした。そのため当時、この「目新しい」料理を食べる際には、箸ではなくフォークとナイフが使われていたのです(阿古, 2021)。
とんかつの起源については諸説ありますが、岡田(2021)によると、森島中良(もりしま ちゅうりょう)が著し1787年に出版された『紅毛雑話(こうもうざつわ)』の中の『オランダ人の料理献立』に登場するホールコットレッツ(豚カツレツ)が、とんかつの原型であると考えられているようです。
今日、とんかつは世界的に和食として認識されている
とんかつは独自の解釈や提供スタイルを通じて少しずつ進化を遂げ、今では日本人だけでなく外国人からも「和食」として広く認識されるようになりました。
日本人は試行錯誤を重ねながら、天ぷらの揚げ方の技術にヒントを得て、とんかつの「ディープ・ファット・フライング」の調理法を改良してきました。その過程で、ヨーロッパ風の細かく滑らかなパン粉ではなく、日本独自の粗めのパン粉を使用するようになり、肉も薄切りから厚切りへと変化していきました(岡田, 2021)。
さらに、もともとイギリスのウスター州で生まれたウスターソースも、日本で独自の進化を遂げました。日本人はこのイギリス生まれのウスターソースに野菜や果物を加えてうま味を強め、とんかつやご飯に合うように、「とろみ」をつけたのです。また、温野菜ではなく、千切りの生キャベツがとんかつの付け合わせとして定着しました(阿古, 2021)。
この「とんかつと千切りキャベツ」の絶妙な組み合わせについて、次のように表現されています。
「キャベツをザクザク噛んで口中の油を洗い、また頬張る。似た歯触りでありながら、味わいは異なる。そして、両者の甘みは非常に近い。舌の感覚を惑わすことなく、とんかつの旨みが堪能できる。」(岡田, 2021)。
福岡の「味のかつえだ」で一汁一菜スタイルのとんかつ定食を堪能しよう
とんかつは西洋料理をルーツに持ちながらも、現在では一汁一菜スタイルで箸を使って食べることが一般的になっており、初心者が和食の基本を体験するのに最適な一品です。
一汁一菜とは、ご飯、一汁(通常は味噌汁)、そして主菜となるおかず一品から成り立つ構成でこのスタイルは和食の基本形とされています。漬物が添えられることも多いですが、これはおかずには数えられないこともあります(土井, 2021)。
福岡の「味のかつえだ」は、博多駅や福岡空港からも遠くない便利な立地のとんかつ専門店です。ここではすべての定食が一汁一菜スタイルで提供されており、豚汁または赤だしのどちらかを選ぶことができます。
一般的な日本の飲食店よりも量が多いためか、特にランチタイムには地元のビジネスマンで賑わっています。
脂肪分が気になる健康志向の方にはヒレカツ定食(豚ヒレ肉のとんかつセット)が、濃厚でジューシーな味わいを楽しみたい方にはロースカツ定食(豚ロース肉のとんかつセット)がお勧めです(岡田, 2021)。また、エビフライ(エビに小麦粉、溶き卵、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理)定食もおいしいです。
なお、「味のかつえだ」はこぢんまりとした地元の食堂のため、現金のみの支払いとなっていますので、その点にはご注意ください。

一汁一菜とはご飯、汁物(一般的には味噌汁)そして主菜となるおかず一品で構成される、日本の基本的な食事スタイルです。
福岡で最も美味しいちゃんぽんを提供するとの評判も…
名前に「かつ」がついていることからもわかるように、「味のかつえだ」はとんかつ専門店です。しかし、意外なことに、長崎風ちゃんぽんでも有名になりました。
これは、創業者の時枝宣雄さんがまかない料理として提供していたちゃんぽんが、その美味しさから口コミで広まり、正式なメニューに加わったことから始まったそうです(西日本新聞, 2022)。現在では、福岡のみならず、広範囲にわたりちゃんぽんが美味しい店としても知られています。
ちゃんぽんとは?
ちゃんぽんとは、福岡の南西に位置する長崎県の郷土料理です。豚肉、エビ、イカ、キャベツ、もやし、玉ねぎ、人参、キクラゲなど、地域で採れた新鮮な具材がたっぷりと入った心温まる麺料理で季節によっては、アサリやカキが加えられることもあります(JTBパブリッシング, 2015年)。
江戸時代の鎖国政策下で、日本が孤立していた時期、長崎は唯一外国と貿易が行われていた港町でした。そのため、貿易や炭鉱業、軍港としての役割から、さまざまな地域から人々が集まり、新しい影響や多様な文化が交じり合う開かれた場所となりました。この背景が影響したせいか、ちゃんぽんの料理法には厳格なルールがないのです。つまり、ちゃんぽんと呼ばれるために必ずしも特定の具材を入れなければならないという決まりはないのです(矢野、2015年)。
実際、長崎の家庭ごとに独自のバージョンのちゃんぽんがあり、その味付けや調理法、使用する具材にもこだわりがあり、自分の家のちゃんぽんが最も美味しいと信じている家庭が多いと言われています(矢野、2015年)。
「ちゃんぽん」という名前の由来には、長崎の多様な歴史的背景を反映したいくつかの説があります。例えば、「簡単な食事」を意味する中国語の「喰飯(shān pǔ lóng)」が、時を経て発音が変化したという説があります。また、「混ぜる」や「ブレンドする」という意味を持つポルトガル語の「chanpon」に由来するという説もあります(農林水産省、2025年)。

ちゃんぽんとは地域の新鮮な食材をたっぷり使った、心温まる麺料理です。
ちゃんぽんに入っている、弾力のあるピンク、白、時には緑色の具材とは?
外国から訪れた友人をちゃんぽんを食べに連れて行くと、ほぼ必ず「この弾力のあるピンクや白、時には緑色の具材は何?」と聞かれます。
実はこのカラフルでモチッとした食感のものは「はんぺん」と呼ばれる魚のすり身で作られた練り物です。主に「エソ」と呼ばれる魚が原料として使われていますが(順天の娘のブログ, n.d.)、タラやグチなどが使用されることもあります(石橋蒲鉾店, n.d.)。
長崎のはんぺんは、県外で一般的に見られる、サメ肉と大和芋を混ぜて蒸した白いはんぺんとは異なります(長崎Webマガジン「ナガジン」, n.d.)。長崎のはんぺん自体が特産品であり、ちゃんぽんに彩りを添える具材として欠かせない存在です。
ラーメンと比べて試すべき面白い選択肢
もしかしたらあなたが福岡に来た目的の一つはラーメンかも知れません。何しろ福岡は世界でも有数のラーメンの聖地ですから。でも、1899年に長崎で誕生したちゃんぽんの起源について知ると、実はちゃんぽんは「ラーメン」の一種とも言えることに気づくかも知れません。
地元の伝承によると、中国料理店「四海樓(しかいろう)」の店主、陳平順(ちん へいじゅん)氏が、日本で学ぶ中国人留学生のために、安価で栄養価の高い料理を提供しようと考えたのが、ちゃんぽんの始まりだったそうです。彼は、野菜の切れ端や肉の端材を炒め、中国麺を加えてスープで煮込み、一つの鍋だけで手軽においしい料理を作り上げました(農林水産省、2025年)。
福岡を訪れたなら、ぜひラーメンだけでなく、ちゃんぽんも試してみることをお勧めします。ちゃんぽんはラーメンよりも具材が豊富でボリュームがあり、麺も太めなのが特徴です。もしかすると、ラーメン以上にあなたの好みに合うかも知れません。
味のかつえだ(平尾・福岡)
- 住所:
〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾3丁目7-22
西鉄平尾駅より徒歩8分
- 営業時間:
11:30 AM – 2:30 PM, 6:00 PM – 9:00 PM
- 定休日:
日曜日、祝日
- 喫煙:
禁煙
- 電話番号:
092-523-0296
- 価格帯:
¥1,000~¥1,999
- 留意点:
現金のみ可
参考文献
土井, Y. (2021). 一汁一菜でよいという提案. 新潮社
石橋蒲鉾店. (n.d.). 片半ぺん [Blog post]. 石橋蒲鉾店. http://ishibashi-kamaboko.com/kamaboko/katahanpen/
JTB パブリッシング. (2015). 楽々九州 (2016年版). JTBパブリッシング.
順天の娘. (n.d.). はんぺん [Blog post]. 長崎ちゃんぽんと皿うどんのお店–順天の娘のブログ. http://juntengirl.blog134.fc2.com/blog-entry-77.html
農林水産省. (2025). うちの郷土料理: 次世代に伝えたい大切な味–長崎県チャンポン. 農林水産省. https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/46_8_nagasaki.html
長崎ウェブマガジン「ナガジン」(n.d.). 長崎土産名鑑Vol.1. 冬が食べどき!長崎かんぼこ. 長崎市広報広聴課. https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/hakken0212/index.html
西日本新聞 (2022, April 15). とんかつ店の名物チャンポン 兄弟で味守り継ぐ 味のかつえだ(福岡市中央区). 西日本新聞. https://www.nishinippon.co.jp/item/n/907542/